全学協定交換留学:ウーロンゴン大学(2024年2月〜2024年12月)University of Wollongong
私が長期留学に挑戦しようと思ったきっかけは、日本の教育を客観的な視点で見てみたいと思ったからです。日本の教育は、礼儀やマナーが身につく、どんなところにいても教育の内容が高いレベルで保障されている等と評価される一方で、詰め込みすぎである、同調圧力が強くてしんどく感じる子が生まれやすい、などの指摘も見られます。特に私が勉強している特別支援教育の分野では、国連から「障害児に対する分離的な教育をやめるように」と勧告されたことが話題になっています。その影響もあり、昨今の教育分野では、海外の教育について取り上げられることが多くなってきました。私は日本の教育と海外の教育のいいところ、課題はどこか、ということを長期的に、かつ多角的に考えたいと思い、長期留学に応募しました。
留学中は、大学の教育学部で幼児教育、初等教育、発達心理、第2言語教育などの授業を履修しつつ、地域の保育園、小学校、特別支援学校などで継続的にボランティアを行いました。授業には講義の部とディスカッションの部がありました。ディスカッションについて行くのはとても大変でしたが、現地の学生の「当たり前」が自分の「当たり前」とずれていることがあったり、日本ではこう考えられているけどオーストラリアではどう考えられているのか、というように課題を投げかけたりして、考えが深まるのを感じ、とても学問が楽しいと思いました。第2言語教育に関する授業では、英語を第2言語とする子どもへの教育を学びながら、それを応用して、日本語を第2言語とする子どもへの支援を最終課題で提出しました。他の学生に比べ資料を集めることなど苦戦した課題でしたが、満足する課題ができ、「リコはこの分野で日本の第一人者になれるかもね!」と言われ、自信がつきました。留学生がほとんどいない授業ばかりでしたが、教授に相談したり、クラスメイトに助けてもらったりしながらなんとか乗り切ることができました。
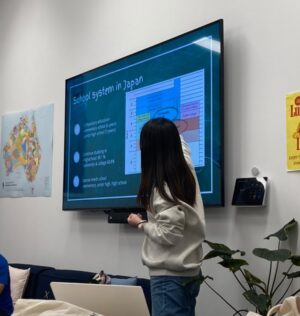
留学生交流サークルで、日本の教育システムについてプレゼンをした時の写真
授業で理論を学びながら、保育園、特別支援学校、小学校でのボランティアを通して、オーストラリアの実際の授業を知ることができました。伝手がない中でボランティア先を見つけることは難しく、何度も現地に足を運んで交渉しました。受け入れてくださった方々や子ども達にはとても感謝しています。元々子どもと遊ぶことや学ぶことが大好きなので、1週間で一番楽しみにしている時間でした。反面、私の英語力不足、子ども理解不足、オーストラリアでの知らないルールなど、悔しい思いをすることもたくさんありました。どの場所でも、意外にも「あっこんなところは日本と一緒なんだ」と思う場面が多かったです。しかし、よく考えてみるとやはり日本と違っているところの方がベースになっており、私自身が戸惑ったりや混乱した場面があったからこそ、共通点が際立っていたのかもしれません。特に、先生が子どもを注意するタイミングが掴めず、私だったら全体に注意するな、というところで注意せず、こんなことで?と思うことで注意されているように思いました。日本の文化と教育で培われた価値観と、オーストラリアの感覚の違いを特に強く感じる瞬間でした。

帰国直前に、2人(自分とインド出身のルームメイト)でお土産を買うためにシドニーまで出かけた時の写真。
授業や遊びの合間に先生に質問したり、資料を教えてもらったりして、家でそのことについて詳しく調べていると、日本で見たり聞いたりしていたいわゆる「海外の教育」とは違った面も見えてきて、もっとすごいと思うことも、課題に感じることもありました。日本から出たからこそ、現地の保育園や学校に飛び込んだからこそ、学べたことだと思います。また、ずっと子どもの様子やノートなどを観察していると、自由に遊んでいることは日本と似ているな、と思いつつ、学んでいる姿は少し違うような気もしました。異なる場所にいる様々な子どもを見ることで、より深く考えることができたように思います。
子ども教育では、長期留学をする人は多数派ではありませんが、私は本当に行ってよかったと思います。留学をしている間は、「せっかく留学先にいるんだから!」と、日本にいる自分だったらブレーキをかけてしまうようなことでも挑戦することができ、結果的に予想以上の学びを得ることができました。オーストラリア国内だけでなく、隣国のニュージーランドの保育園にも見学に行ったことがきっかけで、卒論で研究したいことが出てきました。将来は英語を使う仕事ではなく、小学校教師になりたいと思っていますが、直接的ではなくとも、何かこの1年間に学んだことが子ども達に還元できたらいいなと思っています。

特別支援学級でボランティアで、注意をした子に「No Rico」と書かれている。思い切り拒否されているが、名前を覚えられ、意思を伝えてくれたことが嬉しかった。
増田 莉子 MASUDA Riko(子ども教育学科 4年)